読書についての随想
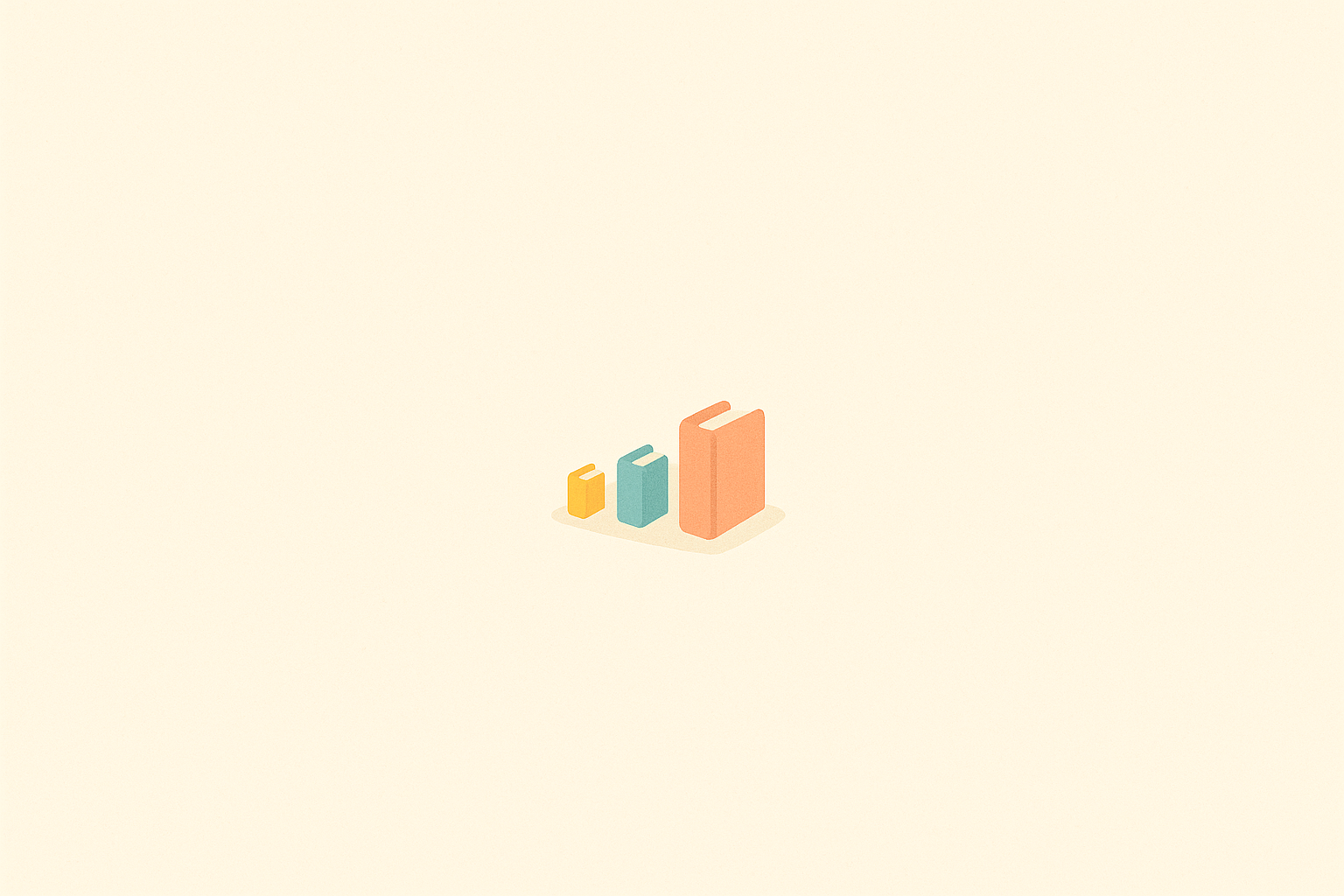
私の人生における「カテゴリ別 時間消費ランキング」は睡眠の次にゲームであること間違いなし、という程度にはゲームに時間を費やしてきた(実際に測定すればそうでもないだろう)が、社交界などのフォーマルな場で口ひげを蓄えた御仁に「貴殿、ご趣味は――?」と尋ねられれば「読書を少々――」と少しアンニュイな表情を携えて呟くくらいには、読書が好きだ。
私的三種の神器ルーチンと読んでいる本の紹介
読書ペースは月に1,2冊ほどで、小説、新書、実用書が中心である。基本的には3冊同時進行で、「集中しなくても読める本」、「そこそこ集中しないと読めない本」、「紙とペンを使わないと読めない本」の3種を1冊ずつ読んでいる。参考までに、今現在読んでいる本を紹介する。
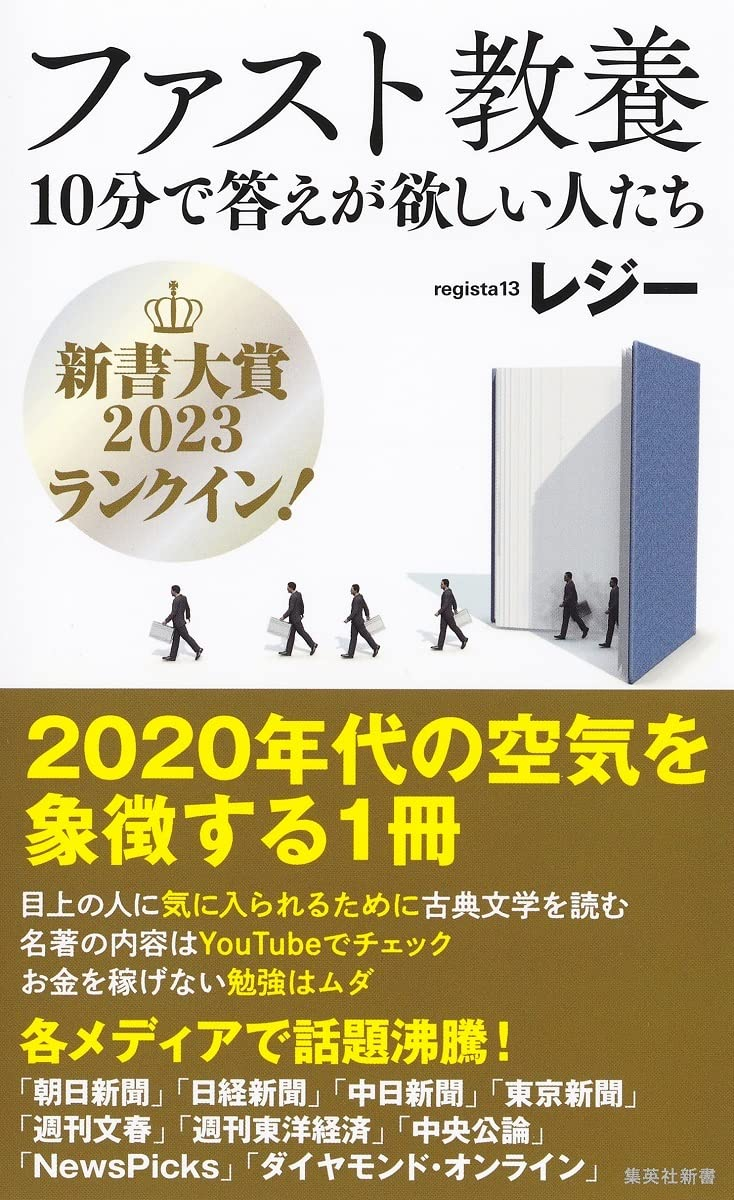
ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち (集英社新書)
【「教養=ビジネスの役に立つ」が生む息苦しさの正体】 社交スキルアップのために古典を読み、名著の内容をYouTubeでチェック、財テクや論破術をインフルエンサーから学び「自分の価値」を上げろ───このような「教養論」がビジネスパーソンの間で広まっている...
これは「そこそこ集中しないと読めない本」。本屋に「教養としての〇〇」といった表題の本が増えてきたので手にとった。なお、海羚羊はビジネスなどで用いる前提の打算的な「教養」についてはいささか懐疑的である。
ビジネスのツールとして役立てるために文化的な知識を学ぶことを「教養」と呼び、純粋な知的好奇心から得た知識、精神的な豊かさを指す本来の「教養」という言葉の意味を書き換え、「太宰治」や「ビートルズ」などをお金儲けの道具として使用する前提で触れることは、何かのふとしたきっかけでこれらに触れて心を動かされた人にとっては違和感を感じざるを得ない。
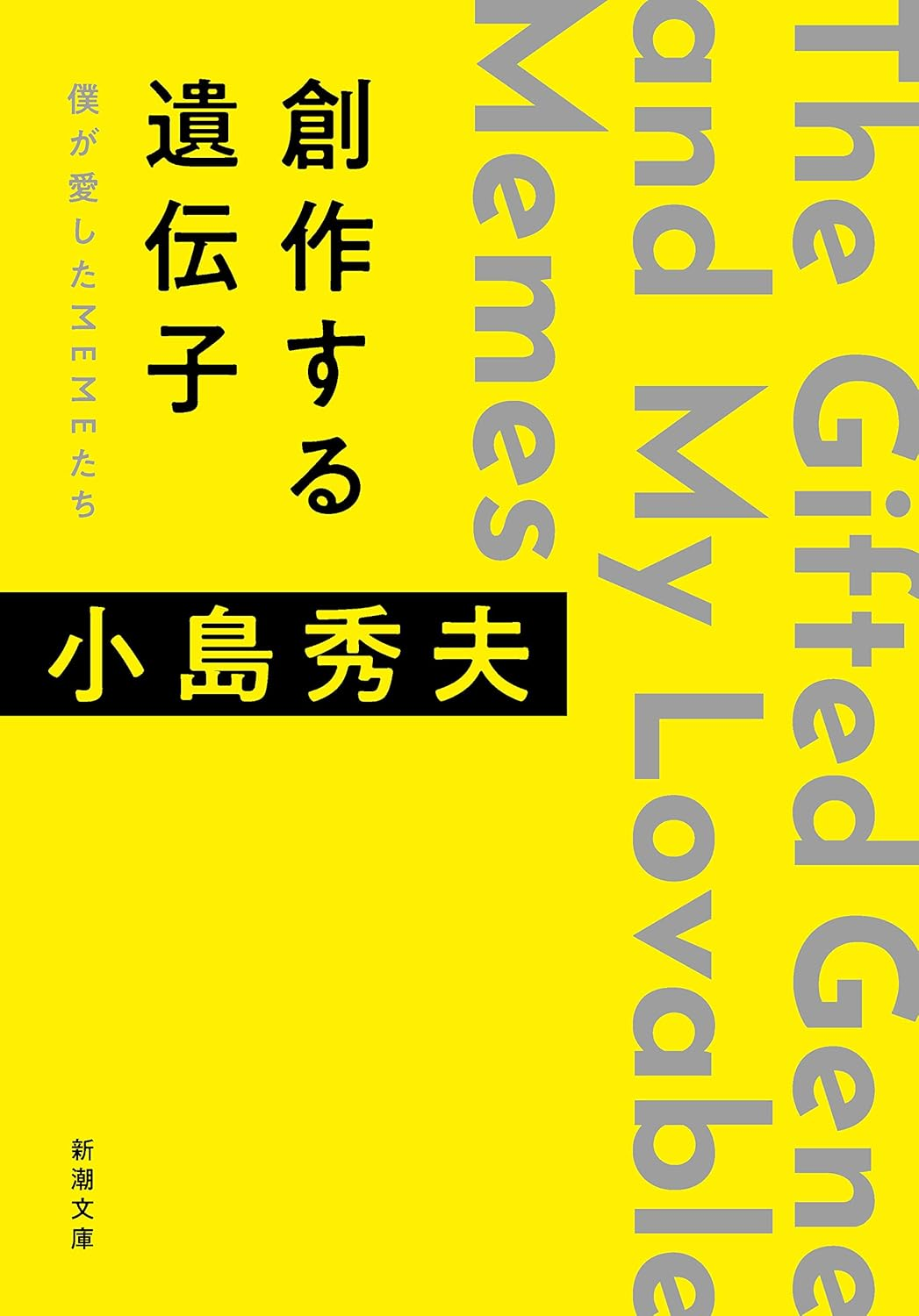
創作する遺伝子 僕が愛したMEMEたち (新潮文庫)
「メタルギアソリッド」を生んだ天才ゲームクリエイターが 己の創作衝動を焚きつける愛すべき小説、音楽、そして映画について語る...
これは「集中しなくても読める本」。最近、「DEATH STRANDING」を40時間ほどプレイしている。本作は、突如として現れた「デス・ストランディング」という現象で滅亡の危機に瀕している21世紀の北アメリカを舞台に、配達人として分断された街や人々を繋ぐ究極のお使いゲームである。このゲーム、世界観設定がかなり凝っていて、「デス・ストランディング」で出現した時間が経過しない「ビーチ」を活用した無時間通信、そこから発生するカイラル物質を使用した技術など、ワクワクする設定がきちんと論理的に設定されており、ゲームを進めるたびに解放される読み物で知得することが出来る。
小島監督といえば、メタルギア、サイレントヒルで有名だが、KONMAIから独立後におそらく自分のやりたいことを詰め込んだ新規IPが退廃的なSFになるとは驚いた。大好物である。
そんなコジカンが焚き付けられた作品について語った本書は、読まなければ!
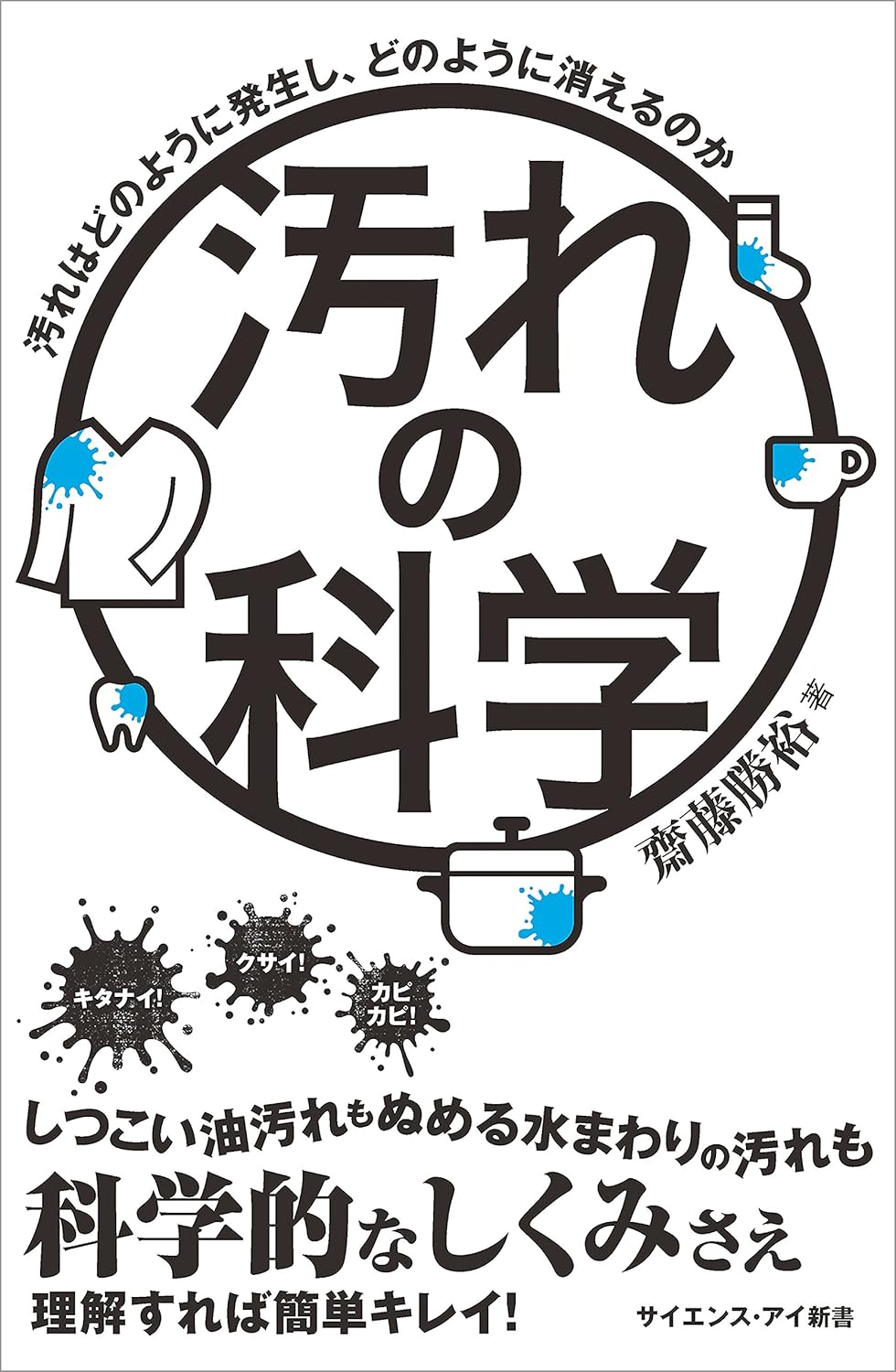
汚れの科学 汚れはどのように発生し、どのように消えるのか (サイエンス・アイ新書)
キタナイ! クサイ! クサイ! なぜ汚れが発生するのか、そして、どのように落とせるのか、防げるのか 本書は汚れの発生と消失を、化学的に解説する書である...
「紙とペンを使わないと読めない本」......、とは厳密には異なるが、本質的には学術的な本と認定して読んでいる。
「ぜんぜんわからない。俺たちは雰囲気で掃除をやっている」とインベスターZの神代の面持ちで家を掃除することに終止符を打つために読み始めた。なお、元ネタとされる当該セリフは本編では一切登場しない。ルフィ「何が嫌いかより、何が好きかで自分を語れよ!」みたいだ。
重曹やクエン酸で汚れが落ちる原理を、簡単な化学の知識で解説してくれる。セスキとかいうヒカキンの家族みたいな謎に包まれた物質の正体も、この本を読めば知ることができる。
ドッグイヤー
読んでいて少しでも感銘を受けたページにはドッグイヤーをつけるようにしている。良書の場合は耳まみれになって本の厚さがひとまわり増える。ドッグイヤーをつけた裏面にもさらに耳をつけたい場合は下側につける。90°右回転させた犬が出来上がる。海羚羊脳内ではシェルティだ。
ドッグイヤーをつけることで、自らの所有物としての「本」の価値を高めている。本屋に並ぶ本と、自宅の本棚に並ぶ本を差別化できることが、海羚羊が本を購入する理由のひとつだ。
外部記憶装置としての読書メモ
折ったページは後にGoogleスプレッドシートに読書メモを残す。本のタイトル列、ページ列、引用文の列、それに対するコメント列、といった具合に書いている。日常で「この状況、何かの本で読んだことがあるぞ......!」となった場合にスマホで即座に引けるのが良い。脳味噌の外付けディスク的運用。そもそもインターネットという手軽にアクセスできる巨大集合知が脳味噌の外付けディスクのようなもので、これを自身の能力(知識)の一部だと誤認することで、自己の過大評価がしばしば生じるのだと『知っているつもり 無知の科学』(早川書房)で読んだな。
余談だが、今回のサムネイルの本のイラストはGPT-4oの画像生成機能を用いて生成した。無料版でも数枚程度なら出力できる。ここ1年間の生成AIの進化は特に凄まじく、このブログを構成するHtml、CSSも、WebサーバーもAIに尋ねて構築した部分が少なくない。少し前は「プロンプトエンジニアリング」といって、ようするに「上手な聞き方」みたいなものをマスターした人材が重宝される、といった言説があり、海羚羊もそれが必要となる実感があったが、GPT4oという非常に賢いモデルが登場して、「やっぱりプロンプトエンジニアリング、いらないんじゃね?」となっている。
とはいえ生成AIは現場の空気感というか、質問者がどういう状況なのか読み取ってくれまではしないので、「知識豊富な超優秀新入社員」だと思ってプロンプトを投げてやると、思い通りの回答が得られやすい気がする。なんにせよ、生成AIは使い手以上の能力は発揮できないのは確かだ。
